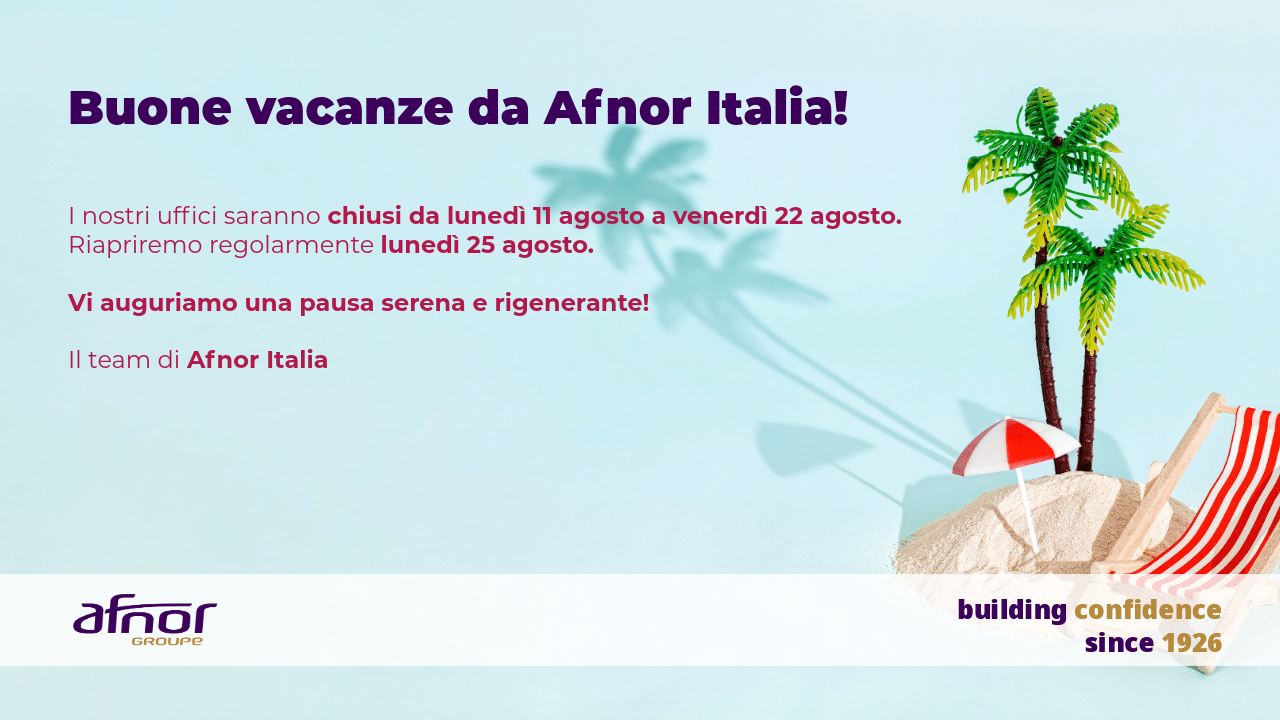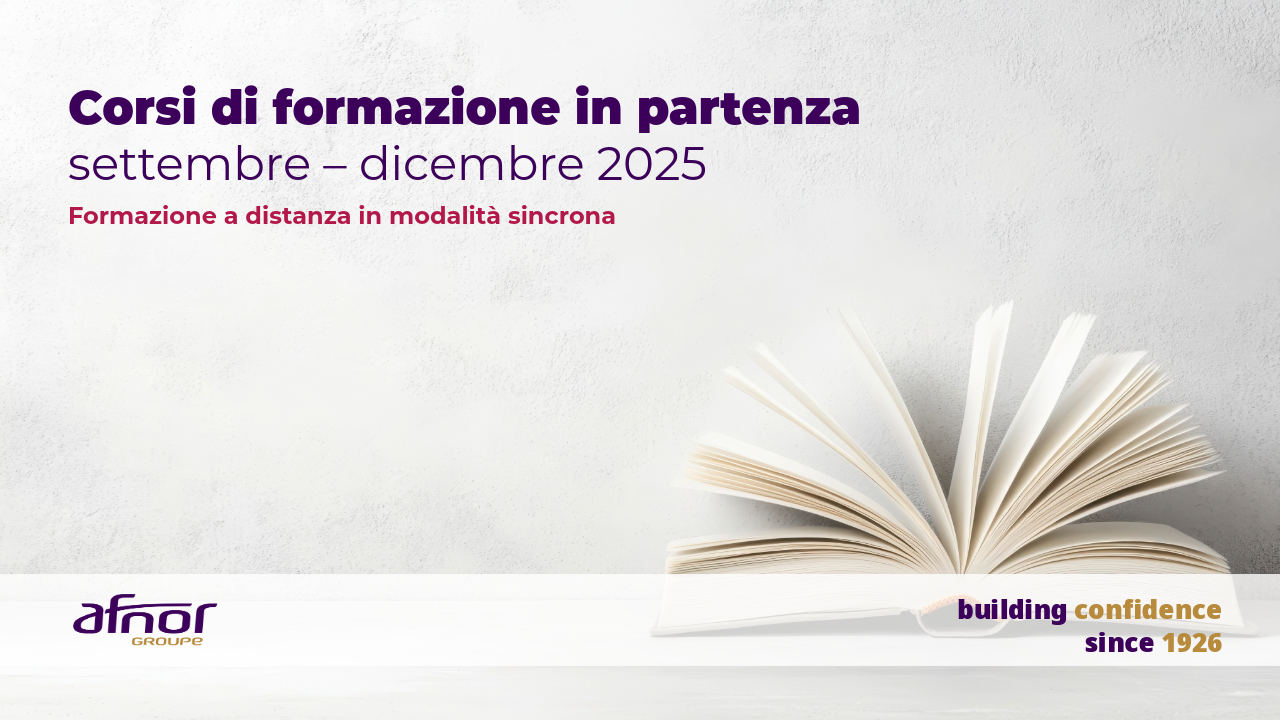品質。人間の資質。サービスの質。製品の質。仕事の質......さまざまなバリエーションがあります。しかし、実際にはどのようなものを指すのでしょうか。専門家であろうと消費者であろうと、品質という概念は様々であり、時にはパラドックス的なまでに乖離し、様々な複雑な概念をカバーしています。2023年に行われたこの大規模な国際調査のために、AFNORグループは37カ国の 1,300人以上の企業の品質意思決定者に質問を行いました。この研究の主な結論を、合計 4つの記事で紹介します。
インタビューによると、"品質 "という概念は4つのポイントで定義されているのが興味深い:
- 質の高い企業文化:B2Bの世界では、組織の男女について語るのが好きです。従業員満足の追求は、回答者の大多数が共有する考え方です。企業文化は、全員が採用し、従わなければならない要件を決定します。
- 品質価値:BtoBとBtoCの世界の交差点で、「倫理的表示」という概念が生まれつつあります。私たちは、組織や製品、サービスが確かな価値観を持っていることを証明したいと考えています。私たちは、共通の価値観と世界に対する共通の理解を共有しています。このような世界では、人々を安心させるために、どのように責任を持つべきかを知る必要があります。したがって、CSR(企業の社会的責任)は、品質ビジョンを支えるテコのように見えます。この品質とCSRの融合において、組織は可能な限り公正な世界を目指していることを示そうとし、その真摯な姿勢を示すことを望んでいます。 品質は、より包括的なものとして見直されています:CSR、持続可能性、地域性、フェアトレード...が品質プロセスに組み込まれ、格付け基準(財務プロファイルの評価、ESG格付けなど)に正式に組み込まれています。 このように、ラベルは、規制を改正する変革ツールとしての品質、組織の本質的なコミットメントを保証する自発的なプライベート・イニシアチブとしての品質を証明するものです。
- 品質に対する認識:BtoCの世界では、品質に対する認識は100%想像上のものです。 私たちは、消費された製品やサービスに対する顧客の経験や満足度というプリズムを通して品質について話します。BtoBの世界では、品質はパフォーマンスの概念と結びついています。
- 品質保証:安全性と透明性という言葉は、品質という言葉に取って代わります。
調査対象国にかかわらず、回答者の37%が、今日の組織にとって最も重要な目的は新規顧客の獲得であると考えており、次いでサービスの卓越性(35%)が僅差で続いています。この2つの側面は非常に重要で、イタリアやインドなど市場が非常にダイナミックで競争が激しい国では、顧客ロイヤルティ(31%)が僅差で続きます。これらの一般的な組織目標は、品質問題と明らかに相関しています。逆に、大半の企業にとって、イメージの向上はそれほど重要でないことは興味深い。これは、より「誠実」で包括的なアプローチを求める消費者のニーズと、この基準を目標の優先事項としていない企業のニーズとの間に存在するギャップを浮き彫りにしています。
品質の定義に向けて...
インタビュー対象者の26%にとって、品質は何よりもまず製品の品質に関する問題です。これは特にブラジル、韓国、メキシコ、インドで顕著です。
2番目と3番目の概念は、回答者の19%が同じように自発的に挙げたもので、特にフランスとブラジルでは、顧客満足と、より効率的な運営への関心です。もうひとつの顕著な事実は、地域の文化的アプローチによって異なる談話のレベルです。例えば、フランスの品質決定者は、この言葉を概念化することに非常に熱心です。要求事項を満たす」「コストを管理する」「期待される利益:ビジネス効率」などです。一方、ドイツでは、製品の堅牢性、ゼロ欠陥という考え方が見られる高度な技術的側面に焦点が当てられます。
日本人は文化的に、顧客やユーザーの期待や要求を超えることを特に大切にします。不良品を出さない」という目標を達成するために、基本に立ち止まることなく、常に枠を超えることを追求します。
インドではこのテーマはあまり成熟していないようで、卓越性よりも顧客に受け入れられる製品という概念が優先されています。メキシコやボリビアでも同様で、品質はより漠然とした位置を占め、正確に定義された基準に基づいているようには見えません。とはいえ、これらの国に共通しているのは、連鎖の末端である消費者や最終顧客について語っていることです。
移動するテーマ、クオリティ
AFNORの調査によると、 品質に関する意思決定者の10人中7人は、品質というテーマが大きく変化していることに同意しています。同時に、品質が安定しているとは必ずしも見られておらず、その定義に同意しているのは60%未満です。
しかし詳細には、このテーマはすべての国でまったく同じように進化しているわけではありません。最も強く動いているのはメキシコで84%。一方、フランスでは悲観論が支配的で、この学問分野に対する見方がやや固定的で、このテーマを取り巻く状況も明確ではありません。同時に、品質という概念が最も収斂しているのはドイツで、その割合は78%。
品質という概念の捉え方には文化が大きく影響しています。
最後に、この概念に特に関心を持つのは、海外に拠点を持つ組織です。そのため、国際的な文脈では、品質がより重要になります。
これは明日の品質への挑戦...。
この調査では、回答者の自発性に訴えかけるため、今後5年間で品質に何が課題となるかを率直に尋ねました。彼らの見解では、明日の課題は次の2つの主要分野に集中すると思われます。 デジタル そしてデータデジタルとデータ。そして、CSRと、より重視されるようになる 環境移行です。CSRは新しい世界であり、トレーサビリティ、デジタル化、環境パフォーマンス、これらは将来の主要課題であり、これらの課題に関与していない企業は多くのことを心配しなければなりません。
この第一部の結論として、品質がカバーする分野は 文化的アプローチや次元が異なることがわかります。フランス人、ドイツ人、イギリス人は、自国、自文化における品質の位置づけについて、同じレベルの言説を持つことはないでしょう。「あるフランス人のインタビューによると、「フランスに品質は存在しない、あるのはパフォーマンス・マネジメントであり、それはグローバルなものだ」と言います。
詳細はこちら